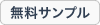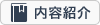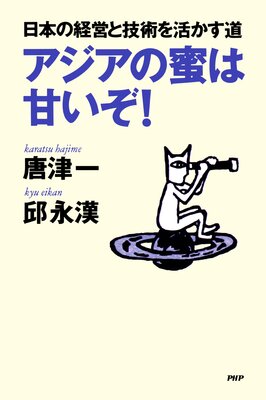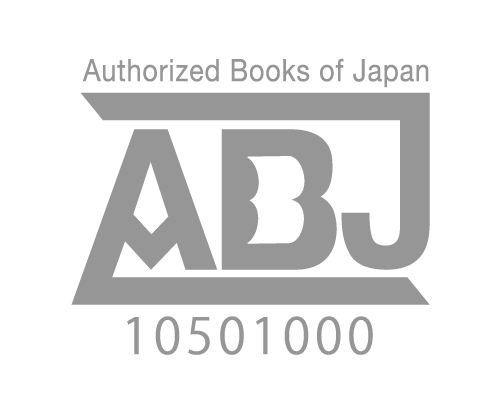検索結果

「今、世界で起きていること」「これから日本におきること」がわかる 地政学×経済学の決定版!
経済が戦争になり、戦争が経済になる。今や日々の生活と安全保障は地続きであることを本書は示す。小泉悠氏推薦(東大先端科学技術研究センター准教授)なぜ、資源を知るために“貿易”や“世界秩序”への理解が必要なのか――複雑化するエネルギー問題を、国際情勢や地政学的要素を経済から捉え直す。
終章に細谷雄一氏(慶應義塾大学法学部教授/地経学研究所 欧米グループ・グループ長)との対談を収録
《本書の構成》
●序章 なぜ、今「地経学」なのか
●第1章 資源を巡る現状と「相互依存の罠」
●第2章 中東情勢とエネルギー問題
●第3章 半導体という戦略物資でみる経済安全保障
●第4章 国際秩序と自由貿易
●終章 資源、戦争、貿易――世界の見取り図をどう手に入れるか 細谷雄一氏(慶應義塾大学法学部教授)との対談
経済が戦争になり、戦争が経済になる。今や日々の生活と安全保障は地続きであることを本書は示す。小泉悠氏推薦(東大先端科学技術研究センター准教授)なぜ、資源を知るために“貿易”や“世界秩序”への理解が必要なのか――複雑化するエネルギー問題を、国際情勢や地政学的要素を経済から捉え直す。
終章に細谷雄一氏(慶應義塾大学法学部教授/地経学研究所 欧米グループ・グループ長)との対談を収録
《本書の構成》
●序章 なぜ、今「地経学」なのか
●第1章 資源を巡る現状と「相互依存の罠」
●第2章 中東情勢とエネルギー問題
●第3章 半導体という戦略物資でみる経済安全保障
●第4章 国際秩序と自由貿易
●終章 資源、戦争、貿易――世界の見取り図をどう手に入れるか 細谷雄一氏(慶應義塾大学法学部教授)との対談

政治とカネなど入口にすぎない! 国民に絶望を与える闇と茶番を憲政史研究家がくまなく解説。
●「派閥解消」「政治改革」は自民党のお家芸。過去、何度となく繰り返された光景である。派閥解消を口にするたび、党内の派閥は強固になっていった。資金に関する自浄作用は、今に至るも見られない。もちろん、彼らが使っているのはわれわれの税金だ。
●「選挙に行く意味がない政治」はどうすれば変わるのか? 堕落しきった「万年与党」が政治を支配してきた要因、国民に残された唯一の希望のありかを探る。
●政権交代を望む声が高まる今、様々な疑問に対する答えが盛り込まれた1冊。
●第1部 これだけは知っておきたい政治改革挫折の歴史
●第2部 あなたが日本の政治に絶望する十の理由
●終章 「ひれ伏して詫びよ」
●「派閥解消」「政治改革」は自民党のお家芸。過去、何度となく繰り返された光景である。派閥解消を口にするたび、党内の派閥は強固になっていった。資金に関する自浄作用は、今に至るも見られない。もちろん、彼らが使っているのはわれわれの税金だ。
●「選挙に行く意味がない政治」はどうすれば変わるのか? 堕落しきった「万年与党」が政治を支配してきた要因、国民に残された唯一の希望のありかを探る。
●政権交代を望む声が高まる今、様々な疑問に対する答えが盛り込まれた1冊。
●第1部 これだけは知っておきたい政治改革挫折の歴史
●第2部 あなたが日本の政治に絶望する十の理由
●終章 「ひれ伏して詫びよ」

特集1は「日本政治の覚悟を問う」。先進民主主義国のなかで例外的に安定していた日本政治が、急速に求心力を失っています。岸田政権は、防衛費の増額や原発再稼働など大きな決断を行なってきましたが、増減税をめぐる姿勢や裏金問題への対応で政権基盤は揺らぎ、派閥の解散が自民党のガバナンスをどう変えるかも不透明です。平成初期とは異なり、自民党の中堅若手からは政治再建への熱意と行動がみられず、野党は四分五裂状態。現在は、混迷のなかで奇妙に「ゆるい政治」が進行していると言えるでしょう。日本政治が混迷を止め、国際秩序を支え、日本社会の未来を拓く推進力となるうえで何が必要なのか、本特集では、岸田文雄首相、立憲民主党の泉健太代表、日本維新の会の馬場伸幸代表、そして高市早苗経済安全保障相など与野党の政治家にビジョンと覚悟を問います。そのうえで、識者による日本政治への建設的な問題提起、また経済界からは日本IBMの山口明夫社長のインタビューを掲載し、転換期の世界における日本政治のあり方を考えます。
特集2は「変わりゆくスポーツの意義」。パリ五輪・パラリンピックを前に、スポーツと社会の関係性の変化などを議論します。また、巻頭には世界でもっとも成功している企業の一つである任天堂の古川俊太郎社長の独占インタビューを掲載しています。
特集2は「変わりゆくスポーツの意義」。パリ五輪・パラリンピックを前に、スポーツと社会の関係性の変化などを議論します。また、巻頭には世界でもっとも成功している企業の一つである任天堂の古川俊太郎社長の独占インタビューを掲載しています。

「弱者男性」の75%は自分を責めている。
“真の弱者”は訴えることすらできない――。
「40代後半でカネもない独身のおっさんに人権なんてないんです。そこにいるだけで怪しくて、やばいんです」
(本書インタビューより)
“真の弱者”は訴えることすらできない――。
「40代後半でカネもない独身のおっさんに人権なんてないんです。そこにいるだけで怪しくて、やばいんです」
(本書インタビューより)
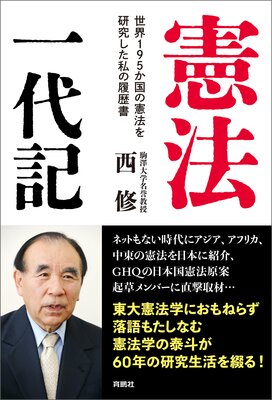
ネットもない時代にアジア、アフリカ、中東の憲法を日本に紹介、
GHQの日本国憲法原案起草メンバーに直撃取材…
東大憲法学におもねらず落語もたしなむ憲法学の泰斗が60年の研究生活を綴る!
私の最大の特色は、実際に連合国総司令部(GHQ)で日本国憲法の原案を作成した8人を含む「歴史の証人たち」47人とインタビューしたこと、米国の国立公文書館をはじめあちらこちらの図書館や研究所、記念館のみならず、英国の国立図書館にまで足をのばして取得した一次資料を中心とする日本国憲法成立過程の研究と、世界のすべての国々を対象にした比較憲法の探究にあると思っています。
そして、しろうと落語家として私の高座を多くの人たちに楽しんでいただいた経験は、他の憲法学者にないだろうと思います。本書にいくつか挙げたユーモアを楽しんでいただけたら幸いです。(あとがきより)
(本書の内容)
第1章 憲法学研究の端緒
第2章 学会の設立と在外研究
第3章 比較憲法学の探究
第4章 日本国憲法成立過程研究の深化
第5章 憲法9条の正しい解釈への模索
第6章 憲法論議の指標
第7章 憲法改正へ向けて
終 章 私の近況報告
GHQの日本国憲法原案起草メンバーに直撃取材…
東大憲法学におもねらず落語もたしなむ憲法学の泰斗が60年の研究生活を綴る!
私の最大の特色は、実際に連合国総司令部(GHQ)で日本国憲法の原案を作成した8人を含む「歴史の証人たち」47人とインタビューしたこと、米国の国立公文書館をはじめあちらこちらの図書館や研究所、記念館のみならず、英国の国立図書館にまで足をのばして取得した一次資料を中心とする日本国憲法成立過程の研究と、世界のすべての国々を対象にした比較憲法の探究にあると思っています。
そして、しろうと落語家として私の高座を多くの人たちに楽しんでいただいた経験は、他の憲法学者にないだろうと思います。本書にいくつか挙げたユーモアを楽しんでいただけたら幸いです。(あとがきより)
(本書の内容)
第1章 憲法学研究の端緒
第2章 学会の設立と在外研究
第3章 比較憲法学の探究
第4章 日本国憲法成立過程研究の深化
第5章 憲法9条の正しい解釈への模索
第6章 憲法論議の指標
第7章 憲法改正へ向けて
終 章 私の近況報告
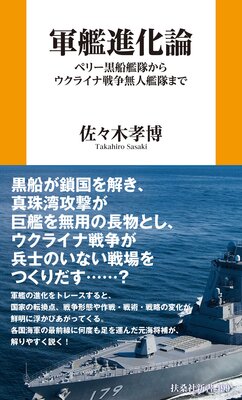
黒船が鎖国を解き、真珠湾攻撃が巨艦を無用の長物とし、ウクライナ戦争が兵士のいない戦場をつくりだす……?
軍艦の進化をトレースすると、国家の転換点、戦争形態や作戦・戦術・戦略の変化が鮮明に浮かびあがってくる。各国海軍の最前線に何度も足を運んだ元海将補が、解りやすく説く!
「砲艦外交」のための軍艦→「敵よりも大砲打撃力の勝る軍艦」が中心、大艦巨砲主義の芽生え→「大艦巨砲主義の中心となる戦艦」が中心、艦隊決戦が海戦の雌雄を決する→「戦艦(大艦巨砲主義:艦隊決戦)」から「空母(空母機動部隊による航空作戦主流)」へ→「空母機動部隊主流は変化なしも、ミサイル対応艦の必要性増大」……「イージス艦」の登場・「ステルス艦(艦上の突起物がなくレーダーを反射にくい)」の登場→「空母主流」「イージス艦の有用性」に変化なしも、「弾道ミサイル対応イージス艦」の必要性増大→「現有艦艇」の有用性は変わらずも、「無人艦隊」による海戦のブレークスルー――という変遷を詳しく解説。
第一章 海軍黎明期の軍艦
第二章 日清・日露戦争時の軍艦
第三章 建艦競争期および海軍軍縮条約期の軍艦
第四章 第二次世界大戦時の軍艦
第五章 第二次世界大戦後・米ソ冷戦期の軍艦
第六章 ポスト冷戦期の現代戦における各国の軍艦
第七章 有人艦艇から無人化艦艇・AI化艦艇の時代へ
軍艦の進化をトレースすると、国家の転換点、戦争形態や作戦・戦術・戦略の変化が鮮明に浮かびあがってくる。各国海軍の最前線に何度も足を運んだ元海将補が、解りやすく説く!
「砲艦外交」のための軍艦→「敵よりも大砲打撃力の勝る軍艦」が中心、大艦巨砲主義の芽生え→「大艦巨砲主義の中心となる戦艦」が中心、艦隊決戦が海戦の雌雄を決する→「戦艦(大艦巨砲主義:艦隊決戦)」から「空母(空母機動部隊による航空作戦主流)」へ→「空母機動部隊主流は変化なしも、ミサイル対応艦の必要性増大」……「イージス艦」の登場・「ステルス艦(艦上の突起物がなくレーダーを反射にくい)」の登場→「空母主流」「イージス艦の有用性」に変化なしも、「弾道ミサイル対応イージス艦」の必要性増大→「現有艦艇」の有用性は変わらずも、「無人艦隊」による海戦のブレークスルー――という変遷を詳しく解説。
第一章 海軍黎明期の軍艦
第二章 日清・日露戦争時の軍艦
第三章 建艦競争期および海軍軍縮条約期の軍艦
第四章 第二次世界大戦時の軍艦
第五章 第二次世界大戦後・米ソ冷戦期の軍艦
第六章 ポスト冷戦期の現代戦における各国の軍艦
第七章 有人艦艇から無人化艦艇・AI化艦艇の時代へ
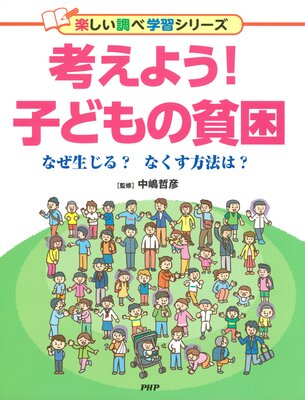
「子どもの貧困」とは、17歳以下の子どもが、その国のちょうど中間の所得の半分以下の所得しかない家庭で暮らし、相対的貧困の状況に置かれていることをいいます。日本では6人に1人の子どもが貧困状態にあります。なぜ、こうした貧困が生じるのでしょう? 日本社会の問題点を示すとともに、どうすれば貧困をなくせるかを考えます。
[第1章]日本の社会と身近な「貧困」
……子どもの貧困の現状/子育てに必要なお金/さまざまな体験をするためのお金/貧困とは、どのような状態?/日本の相対的貧困率 他
[第2章]なぜ、貧困が生じるの?
……低賃金・不安定雇用の増大/所得再分配制度の問題点/社会保障制度の問題点/貧困は自分や親の責任なの?/不安定な雇用の拡大/ワーキング・プアって何? 他
[第3章]なくそう!子どもの貧困
……政府の取り組み/学校教育とお金/子どもを見守る目、見守る心/みんなが自分にできることから 他
[第1章]日本の社会と身近な「貧困」
……子どもの貧困の現状/子育てに必要なお金/さまざまな体験をするためのお金/貧困とは、どのような状態?/日本の相対的貧困率 他
[第2章]なぜ、貧困が生じるの?
……低賃金・不安定雇用の増大/所得再分配制度の問題点/社会保障制度の問題点/貧困は自分や親の責任なの?/不安定な雇用の拡大/ワーキング・プアって何? 他
[第3章]なくそう!子どもの貧困
……政府の取り組み/学校教育とお金/子どもを見守る目、見守る心/みんなが自分にできることから 他

特集1は「日本企業の夜明け」。今年2月、日経平均株価がバブル期につけた史上最高値を、じつに34年ぶりに更新して大きな話題を呼びました。この動きをうけて、「日本企業」の復活が叫ばれましたが、はたして、そのような見方は成り立つのでしょうか。「日本企業」あるいは「日本的経営」などの言葉は、かつては「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代があったものの、その後の「失われた三十年」を経て、基本的には悲観的なニュアンスで用いられてきました。他方で、近年では海外で日本の企業に注目する動きがあるのも事実です。日本の企業と経営の「強み」と「課題」について、特集であらためて検討します。日本の企業のポテンシャルを力強く語るウリケ・シェーデ氏のインタビューや、「日本企業」「日本的経営」という語り口そのものに疑義を呈する楠木建氏の論稿などを掲載するほか、新著『世界は経営でできている』がベストセラーの岩尾俊兵氏の論稿などは必読です。特集2は「なぜ中東は混乱するのか」。イスラエルとイランの対立でさらに緊迫化する中東情勢について、日本人が見落としがちな混乱の淵源に多角的に迫ります。そのほか、文化外交について語る上川陽子外務大臣のインタビューや、頼清徳新総統の人物評などを述べた台湾の陳水扁元総統の独占インタビュー第二弾にも、ぜひご注目ください。
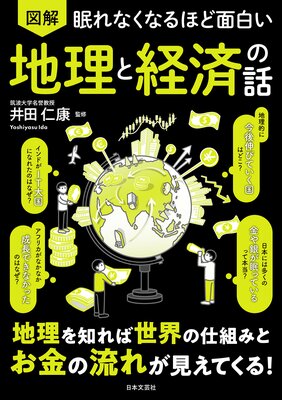
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
【累計300万部突破!『眠れなくなるほど面白い図解シリーズ』経済ジャンル最新刊 世界のニュースもお金の流れも、地理がわかればもっと面白い!『地理と経済の話』】
昨今、地理的条件から政治を分析する「地政学」が注目を集めています。国土の形や立地、隣国との位置関係や気候などから、政治的・軍事的な影響を研究する学問で、世界情勢を紐解くうえで欠かせない考え方といえます。
実は、地理は政治だけでなく、経済にも大きく関わっています。一見繋がりが見えにくい地理と経済の話ですが、・インドでIT産業が特に発展したのはなぜ?・天然資源に恵まれたアフリカがなかなか成長できなかったのはなぜ?・中国やインドに続いて今後さらに伸びていく国はどこ?・中東で大量の石油が採れるのはなぜ?これらはすべて「地理」で説明ができます。
今の世界情勢からこの先世界がどう動いていくかまで、世の中の流れがわかるようになる「経済地理学」が面白く学べる一冊です!
【累計300万部突破!『眠れなくなるほど面白い図解シリーズ』経済ジャンル最新刊 世界のニュースもお金の流れも、地理がわかればもっと面白い!『地理と経済の話』】
昨今、地理的条件から政治を分析する「地政学」が注目を集めています。国土の形や立地、隣国との位置関係や気候などから、政治的・軍事的な影響を研究する学問で、世界情勢を紐解くうえで欠かせない考え方といえます。
実は、地理は政治だけでなく、経済にも大きく関わっています。一見繋がりが見えにくい地理と経済の話ですが、・インドでIT産業が特に発展したのはなぜ?・天然資源に恵まれたアフリカがなかなか成長できなかったのはなぜ?・中国やインドに続いて今後さらに伸びていく国はどこ?・中東で大量の石油が採れるのはなぜ?これらはすべて「地理」で説明ができます。
今の世界情勢からこの先世界がどう動いていくかまで、世の中の流れがわかるようになる「経済地理学」が面白く学べる一冊です!
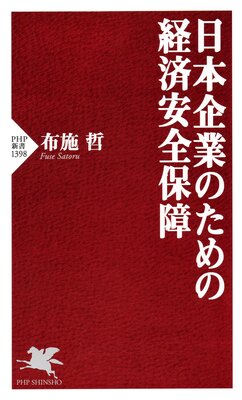
経済安全保障とは何だろうか。
日本企業にとっての経済安全保障の出発点は、米中競争を背景にアメリカや中国、欧州が繰り出す輸出規制や制裁・関税措置などがもたらすリスクを抑えることにある。本書ではさらに一歩進み、企業が経済安全保障をコンプライアンス(法令順守)に加えて事業チャンスに転換させる「攻めの経済安全保障」を考える。経済安保や地政学に関心がありながらも、何をどう理解したらよいか分からない人に、見通しとアクションをもたらす1冊。
著者はテレビ局、インターネット企業を経て現在はNECグループのシンクタンクで働き、ビジネスとパブリックマインドの両立という課題に取り組む。日本を変えたいと思う日本人に、本書の経済安保を通じた意識改革と協働を呼びかけるメッセージが届くことを願う。
〈目次より〉
第1章 経済安全保障とは何か
第2章 攻めの経済安全保障へ
第3章 企業にとっての台湾有事リスク
第4章 デジタル安全保障――「データの武器化」とデジタル敗北
終章 経営に活かす経済安保インテリジェンス
日本企業にとっての経済安全保障の出発点は、米中競争を背景にアメリカや中国、欧州が繰り出す輸出規制や制裁・関税措置などがもたらすリスクを抑えることにある。本書ではさらに一歩進み、企業が経済安全保障をコンプライアンス(法令順守)に加えて事業チャンスに転換させる「攻めの経済安全保障」を考える。経済安保や地政学に関心がありながらも、何をどう理解したらよいか分からない人に、見通しとアクションをもたらす1冊。
著者はテレビ局、インターネット企業を経て現在はNECグループのシンクタンクで働き、ビジネスとパブリックマインドの両立という課題に取り組む。日本を変えたいと思う日本人に、本書の経済安保を通じた意識改革と協働を呼びかけるメッセージが届くことを願う。
〈目次より〉
第1章 経済安全保障とは何か
第2章 攻めの経済安全保障へ
第3章 企業にとっての台湾有事リスク
第4章 デジタル安全保障――「データの武器化」とデジタル敗北
終章 経営に活かす経済安保インテリジェンス
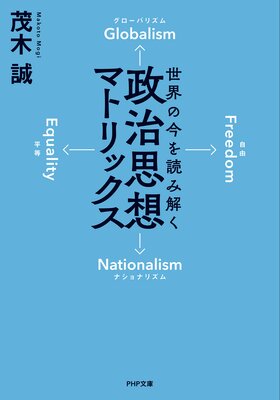
「右派」vs.「左派」では、もはや世界は読み解けない!
カリスマ予備校講師、歴史系YouTuberである著者が、マトリックス図を使って複雑な世界の政治対立をシンプルに整理する。
「朝日新聞は、左がかっている」とか、「産経新聞は、右寄りだ」と、よく言われます。どうやら、政治思想を説明するうえで、もっともベーシックな対立構造が、「右派」vs.「左派」ということのようです。そもそも政治思想において、何が「左」で、何が「右」なのでしょうか?
アメリカの二大政党は、「右」の共和党と「左」の民主党です。共和党は北部の大資本家の支持をバックに成立し、これに対する民主党は労働者の政党として、社会保障政策や労働者保護法の制定など、弱者の側に立った政策を実施してきた――と世界史の教科書には書いてあります。歴史的には、これは間違いではありません。
ところが、2016年のアメリカ大統領選挙では、「右」と思われてきた共和党のドナルド・トランプが「アメリカ人の雇用を取り戻す!」と訴え、もともと民主党支持だった労働者層の支持を受けて当選しました。民主党と共和党の役割が、入れ替わったようにも見えます。同じような現象がヨーロッパ諸国でも起こり、「右」と思われてきた政党が大躍進しています。いったい何が起こっているのでしょうか?
ここまで複雑になると、「右」か「左」かという一次元の直線では説明がつかなくなります。
x軸にy軸を加えた座標軸を考案したのは哲学者であり数学者のデカルトですが、x軸を経済的自由、y軸を政治的自由として、政治思想を二次元座標で表現したのが、米国の政治学者デイヴィッド・ノーランです。本書では、この「ノーラン・チャート」を応用して、さまざまな時代、さまざまな国の政治思想のせめぎ合いを、「政治思想マトリックス」として示していきましょう。複雑に見える世界の政治対立が、実はシンプルなものなのだと、はっきりわかるはずです。
〈目次〉
●第1章:ナショナリズムとグローバリズムの「シーソーゲーム」
●第2章:「米中冷戦」の思想史と強いロシアの復活
●第3章:「超国家EU」崩壊の序曲
●第4章:グローバル化するイスラム革命
●最終章:敗戦後日本の政治思想史と未来
本書は、2020年11月にPHP研究所から刊行された『世界の今を読み解く「政治思想マトリックス」』を改題し、加筆・修正したものです。
カリスマ予備校講師、歴史系YouTuberである著者が、マトリックス図を使って複雑な世界の政治対立をシンプルに整理する。
「朝日新聞は、左がかっている」とか、「産経新聞は、右寄りだ」と、よく言われます。どうやら、政治思想を説明するうえで、もっともベーシックな対立構造が、「右派」vs.「左派」ということのようです。そもそも政治思想において、何が「左」で、何が「右」なのでしょうか?
アメリカの二大政党は、「右」の共和党と「左」の民主党です。共和党は北部の大資本家の支持をバックに成立し、これに対する民主党は労働者の政党として、社会保障政策や労働者保護法の制定など、弱者の側に立った政策を実施してきた――と世界史の教科書には書いてあります。歴史的には、これは間違いではありません。
ところが、2016年のアメリカ大統領選挙では、「右」と思われてきた共和党のドナルド・トランプが「アメリカ人の雇用を取り戻す!」と訴え、もともと民主党支持だった労働者層の支持を受けて当選しました。民主党と共和党の役割が、入れ替わったようにも見えます。同じような現象がヨーロッパ諸国でも起こり、「右」と思われてきた政党が大躍進しています。いったい何が起こっているのでしょうか?
ここまで複雑になると、「右」か「左」かという一次元の直線では説明がつかなくなります。
x軸にy軸を加えた座標軸を考案したのは哲学者であり数学者のデカルトですが、x軸を経済的自由、y軸を政治的自由として、政治思想を二次元座標で表現したのが、米国の政治学者デイヴィッド・ノーランです。本書では、この「ノーラン・チャート」を応用して、さまざまな時代、さまざまな国の政治思想のせめぎ合いを、「政治思想マトリックス」として示していきましょう。複雑に見える世界の政治対立が、実はシンプルなものなのだと、はっきりわかるはずです。
〈目次〉
●第1章:ナショナリズムとグローバリズムの「シーソーゲーム」
●第2章:「米中冷戦」の思想史と強いロシアの復活
●第3章:「超国家EU」崩壊の序曲
●第4章:グローバル化するイスラム革命
●最終章:敗戦後日本の政治思想史と未来
本書は、2020年11月にPHP研究所から刊行された『世界の今を読み解く「政治思想マトリックス」』を改題し、加筆・修正したものです。

財政の将来負担率が黒字、外郭団体への借金はゼロ、自治体最高のムーディーズ格付け。パナソニック創業者の故・松下幸之助、スズキ相談役の鈴木修氏を師と仰ぎ、両者の教え通り自治体の債務を改善した著者。
「市長在任中は、常に経営者としての視点で市政を推進してきました。小さな企画会社を10年ほど経営していましたが、市政は企業経営とよく似ています」
「税収を増やすとともに、最小のコストで市民サービスを最大化するという点では、まさに経営です」(本書「まえがき」より)
「産業政策が命」という必死の取り組み、スタートアップや「出世する街」の実現へ奔走する姿に、他の首長がいかに「経営」を怠っているか、痛感せざるをえない。「政治は利権」という通念を行動によって覆す、刮目の内容。
〈目次より〉
第1章 「やらまいか精神」で全国モデルになる
第2章 財政の将来負担率が黒字になった
第3章 産業の未来を拓く
第4章 出世する街
第5章 自治体と「共進」するグローバル企業
――スズキ株式会社代表取締役社長・鈴木俊宏(対談)前浜松市長・鈴木康友
「市長在任中は、常に経営者としての視点で市政を推進してきました。小さな企画会社を10年ほど経営していましたが、市政は企業経営とよく似ています」
「税収を増やすとともに、最小のコストで市民サービスを最大化するという点では、まさに経営です」(本書「まえがき」より)
「産業政策が命」という必死の取り組み、スタートアップや「出世する街」の実現へ奔走する姿に、他の首長がいかに「経営」を怠っているか、痛感せざるをえない。「政治は利権」という通念を行動によって覆す、刮目の内容。
〈目次より〉
第1章 「やらまいか精神」で全国モデルになる
第2章 財政の将来負担率が黒字になった
第3章 産業の未来を拓く
第4章 出世する街
第5章 自治体と「共進」するグローバル企業
――スズキ株式会社代表取締役社長・鈴木俊宏(対談)前浜松市長・鈴木康友
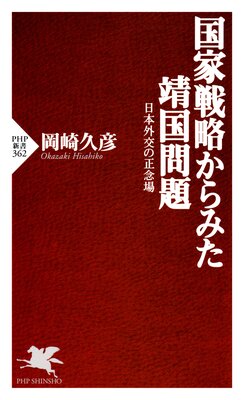
靖国問題で中国に譲歩してはいけない。日本経済が受ける損害、日本人の安全と繁栄に残す禍根、東アジアの平和に及ぼす影響に計り知れないものがあるからだ。そのことは、台湾の戦略的地位を考えてみればわかる。将来、軍事的にも経済的にも強国となった中国が、中台の二者択一を迫ってきたら、日本はいったいどうするのか?
これだけは譲るわけにはいかない。だから今後も日本は、内政不干渉と政教分離の二大原則だけは譲ってはいけないし、ビジネスは立場が弱いから、政府が先に立って守らなければいけないのである――。
2003年春の米国によるイラク攻撃に始まり、小泉総理の第二次訪朝、台湾の陳水扁再選、北朝鮮の核武装宣言、中国の反日暴動、そして昨今の靖国問題に至る激動の時代を、国際情勢分析・情報判断の第一人者が長期的視点から読み解く。
これだけは譲るわけにはいかない。だから今後も日本は、内政不干渉と政教分離の二大原則だけは譲ってはいけないし、ビジネスは立場が弱いから、政府が先に立って守らなければいけないのである――。
2003年春の米国によるイラク攻撃に始まり、小泉総理の第二次訪朝、台湾の陳水扁再選、北朝鮮の核武装宣言、中国の反日暴動、そして昨今の靖国問題に至る激動の時代を、国際情勢分析・情報判断の第一人者が長期的視点から読み解く。
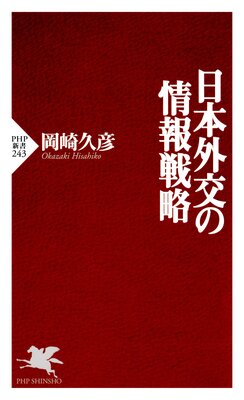
北朝鮮問題、イラク攻撃、さらにアジアのパワーバランスはどうなるのか。21世紀、日本が生き延びるためには情報戦略の整備が不可欠である。具体策として、米国に倣い国家情報官(NIO)の設置を提言。わずか数億円でCIAと並ぶ組織が作れるのだ。アメリカは第二次大戦の教訓から学んで、情報の組織、システムを革命的に改善して情報大国となった。
一方、かつての日本外交の失敗は、日英同盟の廃棄、真珠湾攻撃にあった。それは情報分析力の欠如により、アメリカの本質を読み違えたことにある。情報戦に破れて破滅した日本こそ、情報体制を立て直すべきであったが、戦後は経済再建に手いっぱいで、防衛とともに最も遅れた部門となっている。米国のCIAやNSAと日本の情報機関との格差はおそらく百倍以上であろう、と著者はいう。歴史の教訓を生かし、かつての失敗を繰り返してはならない――。
煮え切らない外交政策を排し、確かな道筋を示した憂国の書。
一方、かつての日本外交の失敗は、日英同盟の廃棄、真珠湾攻撃にあった。それは情報分析力の欠如により、アメリカの本質を読み違えたことにある。情報戦に破れて破滅した日本こそ、情報体制を立て直すべきであったが、戦後は経済再建に手いっぱいで、防衛とともに最も遅れた部門となっている。米国のCIAやNSAと日本の情報機関との格差はおそらく百倍以上であろう、と著者はいう。歴史の教訓を生かし、かつての失敗を繰り返してはならない――。
煮え切らない外交政策を排し、確かな道筋を示した憂国の書。
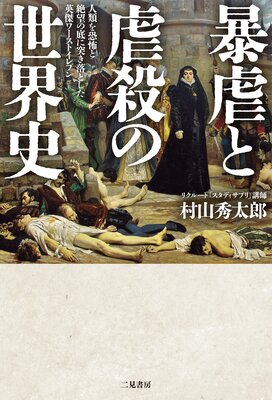
歴史上、人を最も多く殺したのは誰なのか?
暴虐から読み解く異色の世界史!
全ての悲劇はマルクスとダーウィンの手紙のやり取りから始まった……?
ヒトラー、スターリン、毛沢東、コロンブス、ルソー……人類に錯乱と狂気の時代をもたらした11人の英傑たち。
リクルート「スタディサプリ」人気講師がひも解く「悪の世界史」。
フランス人啓蒙思想家ルソーの代表作が、1762年に発表された『社会契約論』ですが、その書のキーワードは「一般意志(人民の意志)」です。中学生の社会科の教科書にあるように「国民主権」という考え方の基礎となりましたが、受け止め方次第で、これほど恐ろしい言葉はありません。
ルソーの思想は穏健に適用すれば、たしかに民主主義につながります。しかし「一般」「人民」の定義を怨みに燃えた特定の「社会階級」に適用した場合には、それは革命と虐殺と略奪に大義を与えるものにもなるのです。
(本書 プロローグより)
《目次》
プロローグ 人類を狂気の時代へ貶めた11人
第1講 宗教と科学、そして思想の変異
第2講 設計主義
第3講 主権論争
第4講 思想のグランドデザイン
第5講 地上における「神の代理人」
第6講 「ハム仮説」というフィクションと悲劇
第7講 「神の国」アメリカの大義
第8講 イスラエルとウクライナ――ふたつの戦争と「死の商人」
暴虐から読み解く異色の世界史!
全ての悲劇はマルクスとダーウィンの手紙のやり取りから始まった……?
ヒトラー、スターリン、毛沢東、コロンブス、ルソー……人類に錯乱と狂気の時代をもたらした11人の英傑たち。
リクルート「スタディサプリ」人気講師がひも解く「悪の世界史」。
フランス人啓蒙思想家ルソーの代表作が、1762年に発表された『社会契約論』ですが、その書のキーワードは「一般意志(人民の意志)」です。中学生の社会科の教科書にあるように「国民主権」という考え方の基礎となりましたが、受け止め方次第で、これほど恐ろしい言葉はありません。
ルソーの思想は穏健に適用すれば、たしかに民主主義につながります。しかし「一般」「人民」の定義を怨みに燃えた特定の「社会階級」に適用した場合には、それは革命と虐殺と略奪に大義を与えるものにもなるのです。
(本書 プロローグより)
《目次》
プロローグ 人類を狂気の時代へ貶めた11人
第1講 宗教と科学、そして思想の変異
第2講 設計主義
第3講 主権論争
第4講 思想のグランドデザイン
第5講 地上における「神の代理人」
第6講 「ハム仮説」というフィクションと悲劇
第7講 「神の国」アメリカの大義
第8講 イスラエルとウクライナ――ふたつの戦争と「死の商人」
![ぼくたちの女災社会[増補改訂版]](https://img.papy.co.jp/lc/sc/item/cover/9-2567494-c400.jpg)
男がもたん時が来ているのだ♂
セクハラ、ストーカー、痴漢冤罪、女性専用車両……。
男たちに襲いかかってきた未曾有のクライシス、それが「女性災害」!!
女のエゴのすべてを呑みこめるほど男は巨大ではないっ♂
女たちに「婚活」させるほど、女性に消極的な「草食系男子たち」……
その原因は「女性災害」の激増にアリ!!!!!?
行きすぎた女尊男卑社会の矛盾を鮮やかに斬る!!
すべての女性は災害である!
刊行から十五年――時代の変遷を経、新たに「十五年目のまえがき」と5本の補論を加えた[増補改訂版]登場。
《目次》
まえがき
十五年目のまえがき
第1章 ぼくたちはいま「女災社会」を生きている
「女災社会」とは何か?
女災社会1.0――セクシャルハラスメント
女災社会2.0――ストーカー
女災社会3.0――痴漢冤罪
女災社会4.0――DV冤罪
第1章補論 ナイトメア「女災社会」の到来
第2章 ぼくたちは「女災社会」をどう生きているのか
女災対策の現在――リスクコミュニケーションの欠如
災害弱者――リスクマネジメントの不在
防災意識の高まり――「萌え」と「草食系男子」
第2章補論 「生命格差」から「愛され格差」へ
第3章 彼女たちは「女災社会」をどう生きているのか
二次女災――非婚化・少子化の本当の理由
水害――負け犬とツンデレっ娘
旱魃――801ちゃんとヤンデレっ娘
第3章補論 「負の性欲と「ジャイ子推し」の時代
第4章 ぼくたちはなぜ「女災社会」に生まれたのか
アニミズム――生贄としての被災者たち
身分制――“ウィメン・オンリー”というアパルトヘイト
女災発生のメカニズム
第4章補論 「女災−1.0」――無(ゼロ)から負(マイナス)へ
終章 迫りくる「メガ女災社会」
女性災害5.0――幼児虐待冤罪
「パラダイムシフト」に向けて――「一人称性/三人称性」
THE END OF FEMALE−HAZARD チ/シキュウ化
ナオンの冬
終章補論 シン・女災――現実(セカイ)対虚構(フェミニズム)
あとがき
セクハラ、ストーカー、痴漢冤罪、女性専用車両……。
男たちに襲いかかってきた未曾有のクライシス、それが「女性災害」!!
女のエゴのすべてを呑みこめるほど男は巨大ではないっ♂
女たちに「婚活」させるほど、女性に消極的な「草食系男子たち」……
その原因は「女性災害」の激増にアリ!!!!!?
行きすぎた女尊男卑社会の矛盾を鮮やかに斬る!!
すべての女性は災害である!
刊行から十五年――時代の変遷を経、新たに「十五年目のまえがき」と5本の補論を加えた[増補改訂版]登場。
《目次》
まえがき
十五年目のまえがき
第1章 ぼくたちはいま「女災社会」を生きている
「女災社会」とは何か?
女災社会1.0――セクシャルハラスメント
女災社会2.0――ストーカー
女災社会3.0――痴漢冤罪
女災社会4.0――DV冤罪
第1章補論 ナイトメア「女災社会」の到来
第2章 ぼくたちは「女災社会」をどう生きているのか
女災対策の現在――リスクコミュニケーションの欠如
災害弱者――リスクマネジメントの不在
防災意識の高まり――「萌え」と「草食系男子」
第2章補論 「生命格差」から「愛され格差」へ
第3章 彼女たちは「女災社会」をどう生きているのか
二次女災――非婚化・少子化の本当の理由
水害――負け犬とツンデレっ娘
旱魃――801ちゃんとヤンデレっ娘
第3章補論 「負の性欲と「ジャイ子推し」の時代
第4章 ぼくたちはなぜ「女災社会」に生まれたのか
アニミズム――生贄としての被災者たち
身分制――“ウィメン・オンリー”というアパルトヘイト
女災発生のメカニズム
第4章補論 「女災−1.0」――無(ゼロ)から負(マイナス)へ
終章 迫りくる「メガ女災社会」
女性災害5.0――幼児虐待冤罪
「パラダイムシフト」に向けて――「一人称性/三人称性」
THE END OF FEMALE−HAZARD チ/シキュウ化
ナオンの冬
終章補論 シン・女災――現実(セカイ)対虚構(フェミニズム)
あとがき

特集1は「不思議の国・ロシア」。投票率約77%、得票率は過去最高を更新する約87%。今年3月、ロシアで行なわれた大統領選挙の結果です。言うまでもなく、勝利したのは現職のウラジーミル・プーチン。われわれから見れば、ウクライナに侵略戦争を仕掛け、なおかつ強権的な手法で国家を統治している人物が、なぜこれほどの支持を受けているのか、不可思議に思えます。他方で、反政府運動家のナワリヌイ氏の死やISによるテロなど、ロシア社会に綻びが見え始めているのも事実。はたして、ロシアという不可思議な国を、私たちはどう理解すればよいのか。彼の国の行動を規定するものは何か。
中西輝政氏と『諜報国家ロシア』で山本七平賞を受賞した保坂三四郎氏が「新しい独裁」を体現しているのはプーチンのロシアであると指摘するほか、日本を代表するロシア文学研究者である亀山郁夫氏はプーチンの行動原理とロシア人のメンタリティに迫ります。
特集2は「『強い野党』はなぜいない?」。いわゆる「裏金問題」以降、自民党への不信が高まっているにもかかわらず、一向に支持率が上がらずに政権交代への期待の声も聞こえてこない野党。現在の課題とあるべき姿を考えます。そのほか、ノーベル経済学賞学者でもあるスティグリッツ教授が、混沌の世界経済と日本経済の課題を論じます。
中西輝政氏と『諜報国家ロシア』で山本七平賞を受賞した保坂三四郎氏が「新しい独裁」を体現しているのはプーチンのロシアであると指摘するほか、日本を代表するロシア文学研究者である亀山郁夫氏はプーチンの行動原理とロシア人のメンタリティに迫ります。
特集2は「『強い野党』はなぜいない?」。いわゆる「裏金問題」以降、自民党への不信が高まっているにもかかわらず、一向に支持率が上がらずに政権交代への期待の声も聞こえてこない野党。現在の課題とあるべき姿を考えます。そのほか、ノーベル経済学賞学者でもあるスティグリッツ教授が、混沌の世界経済と日本経済の課題を論じます。
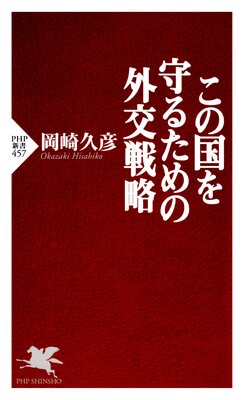
アメリカ、イラク、北朝鮮、韓国、そして中国。激しく揺れ動く世界情勢下で、日本が生き残ることはできるのか? 「靖国問題に終止符を打つには」「遊就館展示修正の真意」「台湾海峡危機は来るのか」「政権維持の秘訣とは」「日米同盟のあり方」「核武装は必要か」――すべての答えは明白である。中国に譲歩はせず、日米同盟を維持せよと著者はいう。国家と国民の安全と繁栄を守るために、いま日本に求められる外交とは――国際情勢分析における第一人者の知的品位に満ちた論が冴える。 日本の核武装論は、日米同盟によって日本の国家と国民の安全と繁栄を守っているという、現に成功している政策の枠内で考えねばならない。(中略)北朝鮮、イランのように米国と対立的な核武装もあるが、それは日本が選択すべき道でないことは明らかである。
(「核戦略論序説――まえがきに代えて」より)
(「核戦略論序説――まえがきに代えて」より)

GHQの思惑通りになった“日出ずる国”
落ち目の日本が知るべき狡猾で欺瞞に満ちた世界の現実
欧州、米国、中国、韓国に学ぶ“普通の国”の立ち振る舞いとは?
第1章 騙され続ける日本人
第2章 「白人」を造ったヨーロッパ人
第3章 アメリカの「黒人」は「白人」です
第4章 中華思想を見習おう
第5章 スネ夫国家「韓国」との付き合い方
第6章 「大阪人」が国際標準です
落ち目の日本が知るべき狡猾で欺瞞に満ちた世界の現実
欧州、米国、中国、韓国に学ぶ“普通の国”の立ち振る舞いとは?
第1章 騙され続ける日本人
第2章 「白人」を造ったヨーロッパ人
第3章 アメリカの「黒人」は「白人」です
第4章 中華思想を見習おう
第5章 スネ夫国家「韓国」との付き合い方
第6章 「大阪人」が国際標準です
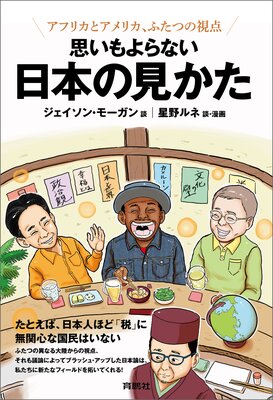
アフリカとアメリカ、ふたつの視点 思いもよらない 日本の見かた
- ジャンル:政治・社会
- 著者:ジェイソン・モーガン 星野ルネ
- 出版社:扶桑社
- 長さ:202ページ
- ポイント数:購入1,700ポイント
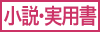
日本の街が綺麗なのは集団主義の成果。日本人ほど税に関心が薄い国民はいない。日本はじつに宗教的な国。「お天道様が見ている」を考えた人は凄い!「火葬」ほど怖いことはない……日本人には思いもよらない指摘が頻出!
アメリカ・ルイジアナで生まれ育った学者と、カメルーンで生まれ、姫路で育った漫画家が日本、アメリカ、カメルーン、そして世界についての大ディベートを展開。我々日本人がスルーしていたこと、「そんな見かたがあったのか」と、思わず膝を叩くこと満載の本書を読めば、世界や国、社会への視野を拡げてくれること間違いなし!
序 章 どこから、ふたりは日本にやってきたのか
第一章 日本と世界の現状
第二章 理想的と言い得る経済モデルはあるのか?
第三章 日本人の政治観
第四章 幸せについて
第五章 文化の壁
第六章 死とサムシング・グレート
アメリカ・ルイジアナで生まれ育った学者と、カメルーンで生まれ、姫路で育った漫画家が日本、アメリカ、カメルーン、そして世界についての大ディベートを展開。我々日本人がスルーしていたこと、「そんな見かたがあったのか」と、思わず膝を叩くこと満載の本書を読めば、世界や国、社会への視野を拡げてくれること間違いなし!
序 章 どこから、ふたりは日本にやってきたのか
第一章 日本と世界の現状
第二章 理想的と言い得る経済モデルはあるのか?
第三章 日本人の政治観
第四章 幸せについて
第五章 文化の壁
第六章 死とサムシング・グレート

子どもたちに増えているネット依存症の症状と影響を示し、ネット依存におちいるきっかけや心理、ネット依存の兆候を確かめるチェックリストを紹介。依存から抜け出す方法についても解説します。
[第1章]インターネットって何?
……インターネットのしくみ/インターネットにつながる社会/インターネットのあやまった利用/インターネットを安全に利用するには 他
[第2章]ネット依存症とは?
……依存症って何だろう?/インターネットに依存する一日/ゲーム依存/コンテンツ依存/つながり依存/情報依存/どうして依存してしまうの?/ネット依存がおよぼす体と心への影響/ネット依存がおよぼす家族や学校への影響/ネット依存がおよぼす社会への影響 他
[第3章]ネット依存にならないために
……依存しない人になるために/依存していませんか? チェックしてみよう/利用状況の確認と目標の設定/ルールを決めよう/工夫してみよう/インターネットと上手につきあう 他
[第1章]インターネットって何?
……インターネットのしくみ/インターネットにつながる社会/インターネットのあやまった利用/インターネットを安全に利用するには 他
[第2章]ネット依存症とは?
……依存症って何だろう?/インターネットに依存する一日/ゲーム依存/コンテンツ依存/つながり依存/情報依存/どうして依存してしまうの?/ネット依存がおよぼす体と心への影響/ネット依存がおよぼす家族や学校への影響/ネット依存がおよぼす社会への影響 他
[第3章]ネット依存にならないために
……依存しない人になるために/依存していませんか? チェックしてみよう/利用状況の確認と目標の設定/ルールを決めよう/工夫してみよう/インターネットと上手につきあう 他

特集1は「韓国の現実」。4月10日、総選挙を迎える韓国。2年前に尹錫悦政権が誕生して以来、それまで険悪な関係が続いていた日韓関係は好転しました。とはいえ、依然として歴史認識問題や竹島問題などの懸案は存在しますし、今後も韓国の対日姿勢は時々の政治状況により変動するはずで、すべての課題が即座に解決するとの見方は楽観的でしょう。隣国であればこそ、両国のあいだには種々の課題や因縁が存在しますが、私たちは韓国がいま直面している「現実」を知ったうえで、いかに戦略目標を共有して、建設的な二国間関係を築くべきなのか。駐韓国大使を務めた冨田浩司氏や、尹政権のポピュリズムを紐解く木村幹氏の論稿などを掲載しています。また、新著『拒否戦略』が話題を呼ぶエルブリッジ・コルビー元米国防次官補代理とハドソン研究所の村野将研究員の特別対談は、東アジアの秩序と日本の安全保障を考えるうえで必読の内容です。特集2は「トランプは世界を壊すか」。日本でも「もしトラ」が本格的に議論され始めているいま、アメリカでトランプ氏が支持を集めている背景や、再登板が現実化したときの世界への影響を考えます。巻頭には、安田峰俊氏による陳水扁元台湾総統への独占インタビューを掲載。中国共産党と対峙し続けてきた陳元総統は、はたして何を語るのか。ぜひご一読ください。
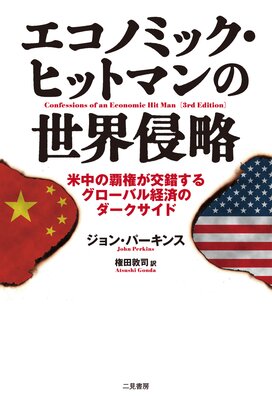
アメリカの弱体化と、中国の台頭。
かつて謀略の最前線にいた元「ヒットマン」だから書けた、「米中経済戦争」の裏側を暴く、衝撃のノンフィクション。
世界的ベストセラーに最新情報を大幅加筆した決定版!
このまま世界は、中国に支配されてしまうのか――
なぜ、資源の豊かな多くの国々が、いつまでも貧しいままなのか――。
本書は、私が長いあいだ感じてきた疑問への理解を助けてくれた。
本書に書かれていることは、複雑で不快な真実かもしれない。
だが私たちは、みずからの責任を簡単に放棄してはならないのだ。
/スティング(ミュージシャン)
これまでに起こった多くの悲劇、その舞台裏を本書は語っています。
そして、このような「死の経済」を、「命の経済」に変えるための方法を。
/オノ・ヨーコ(アーティスト)
「エコノミック・ヒットマン」とは、表向きはコンサルティング会社など企業の社員として働きながら、実際にはアメリカ資本の手先となって、途上国の指導者たちを罠にはめ、天然資源や巨大利権を強奪する「工作員」のことである。
相手が、彼らの「非暴力的な手段(利権や賄賂)」に屈しない場合は、「ジャッカル」つまり「本物の殺し屋」たちの出番となる。
かつて謀略の最前線にいた元「ヒットマン」だから書けた、「米中経済戦争」の裏側を暴く、衝撃のノンフィクション。
世界的ベストセラーに最新情報を大幅加筆した決定版!
このまま世界は、中国に支配されてしまうのか――
なぜ、資源の豊かな多くの国々が、いつまでも貧しいままなのか――。
本書は、私が長いあいだ感じてきた疑問への理解を助けてくれた。
本書に書かれていることは、複雑で不快な真実かもしれない。
だが私たちは、みずからの責任を簡単に放棄してはならないのだ。
/スティング(ミュージシャン)
これまでに起こった多くの悲劇、その舞台裏を本書は語っています。
そして、このような「死の経済」を、「命の経済」に変えるための方法を。
/オノ・ヨーコ(アーティスト)
「エコノミック・ヒットマン」とは、表向きはコンサルティング会社など企業の社員として働きながら、実際にはアメリカ資本の手先となって、途上国の指導者たちを罠にはめ、天然資源や巨大利権を強奪する「工作員」のことである。
相手が、彼らの「非暴力的な手段(利権や賄賂)」に屈しない場合は、「ジャッカル」つまり「本物の殺し屋」たちの出番となる。
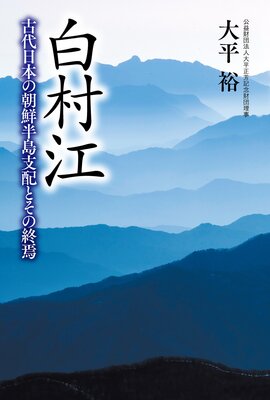
朝鮮半島に新羅・高句麗・百済・任那という諸国が群雄割拠していた時代。古代日本・倭国もまた朝鮮半島と密接にかかわっていた。倭国の植民地ともいえる任那、そして友好関係にあったといわれる百済とはもちろん、新羅や高句麗とも対等に、いやむしろ倭国のほうが上位ともいえる国際関係を堂々と築いていたのだ。隋や唐という大国とも密接にかかわる朝鮮半島はどのような状況だったのか。倭国の立場はどうだったのか。そして古代日本の半島支配の終焉となった白村江の戦いはどのようなものだったのか。朝鮮半島を舞台とした当時の国際関係の実際を解き明かす一冊。
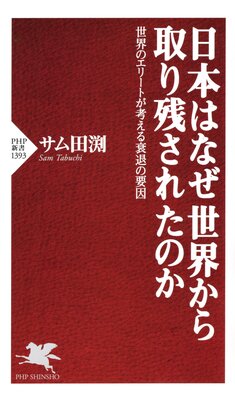
「心に静けさを持つ」といった長所がある一方、「政治家が政府から学ぼうとしない」「短期的、効率的な方法を好み、長期的、漸進的な方法を苦手とする」などの短所も見られる――。
マハティール・マレーシア元首相などエリート33人が日本人の特徴を語り、日本の停滞が続く理由を真摯に考える。さらに日本出身でフロリダ州政府で働いた経験を持つ著者が、過去の日本の経済成長と、現在の停滞の要因である日本独特の価値観「ジャパニズム」を論じる。
【アンケートに真摯に答えた33人のエリートたち】
●アメリカ――フロリダ州元予算管理官、元弁護士、ハーバード大学ロースクール元客員教授など計9人
●ヨーロッパ――フランス財務省高官、ポルトガルの大学教授、イギリス財務省高官など計6人
●アジア――マハティール元首相、日本で大学院を修了し中国・日本で事業を展開している中国人、バングラデシュ政府役人など計10人
●アフリカ――マラウイ政府高官、南アフリカ共和国財務省職員、ソマリアの政府職員など計4人
●日本――国連PPP(官民連携)推進局コンサルタント、外務省系組織勤務など計4人
【目次より】
●日本人の礼儀正しさの背景に見えるもの
●専門分野を持たない低レベルな政治家・政府職員
●傷口に絆創膏を貼るだけの政治
●アメリカのように官の仕事にもノルマを ●マハティール元首相のビジョンと世界観
●提案(1) ウッドペレット生産によるエネルギー政策
●提案(2) 原発をLNG(天然ガス)発電にコンバート
●提案(3) 災害準備対策機関・JEMAの設立
マハティール・マレーシア元首相などエリート33人が日本人の特徴を語り、日本の停滞が続く理由を真摯に考える。さらに日本出身でフロリダ州政府で働いた経験を持つ著者が、過去の日本の経済成長と、現在の停滞の要因である日本独特の価値観「ジャパニズム」を論じる。
【アンケートに真摯に答えた33人のエリートたち】
●アメリカ――フロリダ州元予算管理官、元弁護士、ハーバード大学ロースクール元客員教授など計9人
●ヨーロッパ――フランス財務省高官、ポルトガルの大学教授、イギリス財務省高官など計6人
●アジア――マハティール元首相、日本で大学院を修了し中国・日本で事業を展開している中国人、バングラデシュ政府役人など計10人
●アフリカ――マラウイ政府高官、南アフリカ共和国財務省職員、ソマリアの政府職員など計4人
●日本――国連PPP(官民連携)推進局コンサルタント、外務省系組織勤務など計4人
【目次より】
●日本人の礼儀正しさの背景に見えるもの
●専門分野を持たない低レベルな政治家・政府職員
●傷口に絆創膏を貼るだけの政治
●アメリカのように官の仕事にもノルマを ●マハティール元首相のビジョンと世界観
●提案(1) ウッドペレット生産によるエネルギー政策
●提案(2) 原発をLNG(天然ガス)発電にコンバート
●提案(3) 災害準備対策機関・JEMAの設立
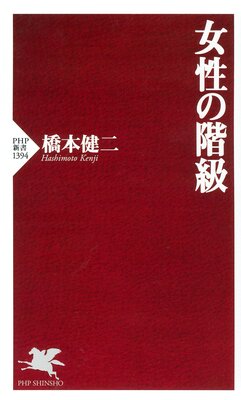
主婦という地位は常に危険と隣り合わせ。
日本の母子家庭の貧困率は、51.4%。実に、2人に1人が貧困である。多くの女性たちは、正規雇用で就職したあと、結婚・出産を機に退職し、専業主婦やパート主婦になるが、夫との離死別などにより簡単に最下層に転落してしまう。
本書では女性にとって大変リスキーな国である日本の実態を、「階級・格差」研究の第一人者がデータを用いて明快に解説する。
職種、年収、持ち家率、教育費、趣味、支持政党、幸福度、飲酒率、メンタル……54のデータから6階級・20グループを徹底分析!
格差是正の鍵を握るのは、女性です!
日本の母子家庭の貧困率は、51.4%。実に、2人に1人が貧困である。多くの女性たちは、正規雇用で就職したあと、結婚・出産を機に退職し、専業主婦やパート主婦になるが、夫との離死別などにより簡単に最下層に転落してしまう。
本書では女性にとって大変リスキーな国である日本の実態を、「階級・格差」研究の第一人者がデータを用いて明快に解説する。
職種、年収、持ち家率、教育費、趣味、支持政党、幸福度、飲酒率、メンタル……54のデータから6階級・20グループを徹底分析!
格差是正の鍵を握るのは、女性です!
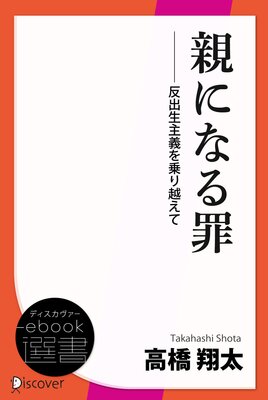
親になる罪―反出生主義を乗り越えて―
- ジャンル:政治・社会
- 著者:高橋翔太
- 出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン
- 長さ:173ページ
- ポイント数:購入1,400ポイント
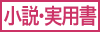
「子供を産む事は悪である」とする「反出生主義」の思想にハマった経験を持つ筆者。
既婚者でありながら、なぜそのような考えに至ったのか。
根底には自らが抱える生きづらさの問題があった。
子供を欲しがる妻との対立と不安定な日々。
そんな中で出会ったのはTwitter(現X)の仲間たち。
同じような苦しみを抱えた人たちが集まるSNSに著者は居場所を見出す。
だが、そこは「思想」とも「哲学」とも無縁な場所であった―
いかにして著者は反出生主義を乗り越えたのか。
元・反出生主義者が主義を捨てるまでの葛藤を描き、反出生主義者の抱える「闇」に迫る。
既婚者でありながら、なぜそのような考えに至ったのか。
根底には自らが抱える生きづらさの問題があった。
子供を欲しがる妻との対立と不安定な日々。
そんな中で出会ったのはTwitter(現X)の仲間たち。
同じような苦しみを抱えた人たちが集まるSNSに著者は居場所を見出す。
だが、そこは「思想」とも「哲学」とも無縁な場所であった―
いかにして著者は反出生主義を乗り越えたのか。
元・反出生主義者が主義を捨てるまでの葛藤を描き、反出生主義者の抱える「闇」に迫る。
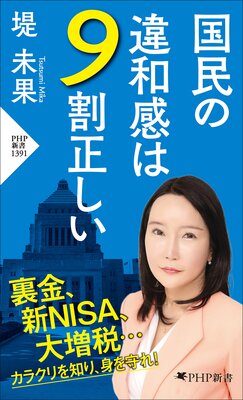
『日本が売られる』『デジタル・ファシズム』『ルポ 食が壊れる』など、数々のベストセラーで注目される国際ジャーナリストが、丹念な取材と調査と分析を重ね、「お金・人事・歴史」の3つから、違和感の裏側を徹底的に暴き、未来を選び取る秘策を明かす!
内容の一部
●報道されないもう一つの「裏金システム」
●大きな悪事を、一般人に気づかせないテクニック
●ゆうちょ、年金、次は新NISAで預貯金いただきます
●防衛費のために通信インフラ(NTT)売ります
●世界一のインフラ技術と「水道管がボロボロ」の違和感
●大事な農地がどんどん売られる
●なぜガザの建物は全て破壊され、住民は皆追い出されるのか?
●「今を生きる」で未来が創れる ――日本人の精神性が世界を救う。
内容の一部
●報道されないもう一つの「裏金システム」
●大きな悪事を、一般人に気づかせないテクニック
●ゆうちょ、年金、次は新NISAで預貯金いただきます
●防衛費のために通信インフラ(NTT)売ります
●世界一のインフラ技術と「水道管がボロボロ」の違和感
●大事な農地がどんどん売られる
●なぜガザの建物は全て破壊され、住民は皆追い出されるのか?
●「今を生きる」で未来が創れる ――日本人の精神性が世界を救う。
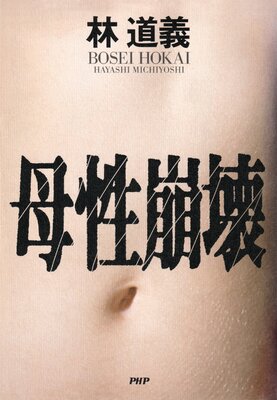
母親によるわが子の虐待・殺害が急増している。炎天下、パチンコ店の駐車場で、幼児を車の中に何時間も置き去りにする母親。男友達と遊び歩き、わが子を栄養失調で死に至らしめる母親。小学生の娘を縛り上げ、夫と友人の三人で打ち殺してしまった母親……。わが子が可愛いと思うのは母親の健全な、普通の姿である。だとするならば、今起きている幼児・児童への虐待は、母親の母性本能の崩壊として見ていかなければならない。ところが、「『母親ならば自分の子が可愛いのが当たり前』という母性本能説が母親を追いつめて、子どもを虐待させる原因になっている」と主張する人々が少なくない。心理学の領域から家庭・教育問題を論じ続けてきた著者は、そうした「母性神話」原因説の誤りを徹底的に批判すると共に、さまざまな角度から母性本能の崩壊を分析する。そして、子どもが可愛くない母親、母親に可愛がられない子どもが、いかにすればなくなるかを探る。

















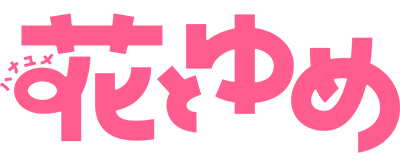

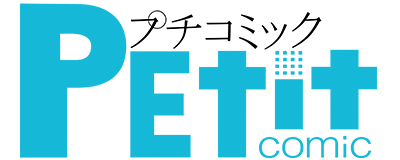












 資源と経済の世界地図
資源と経済の世界地図