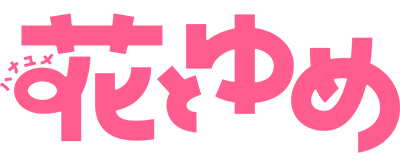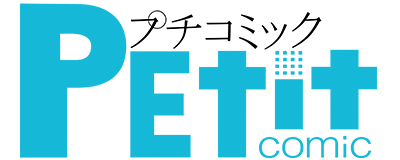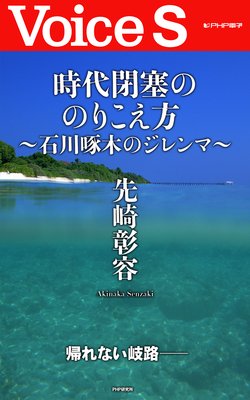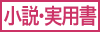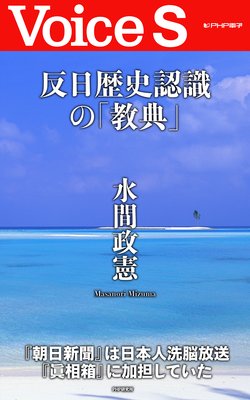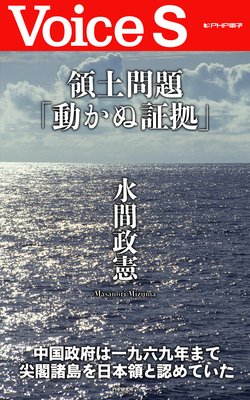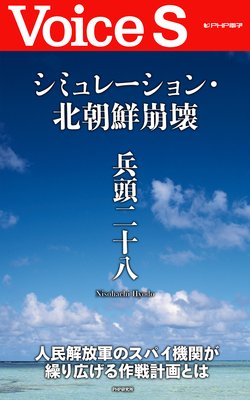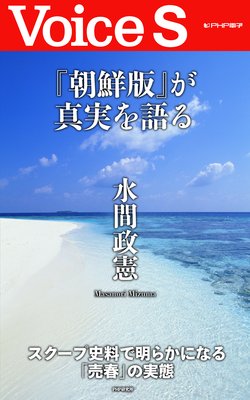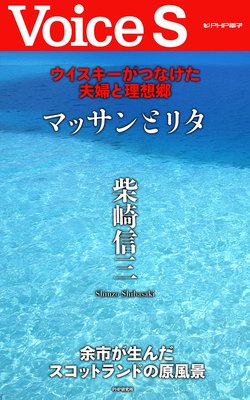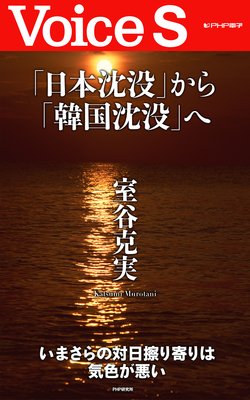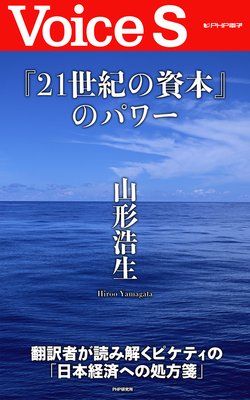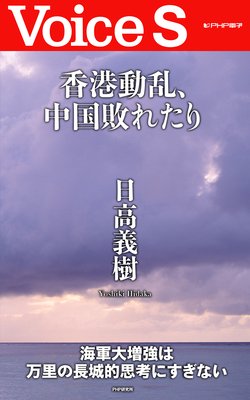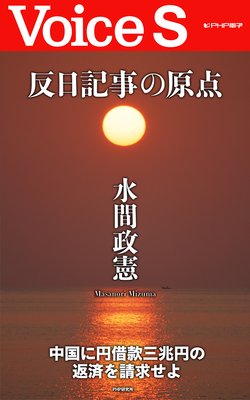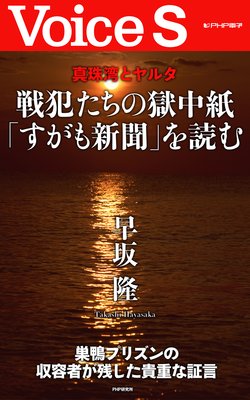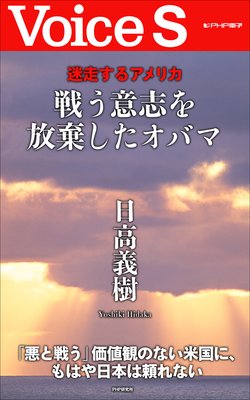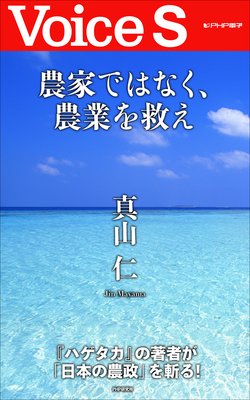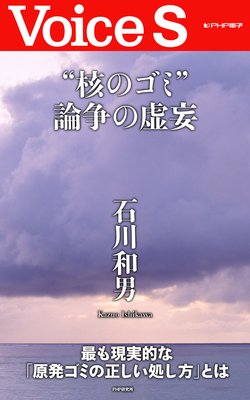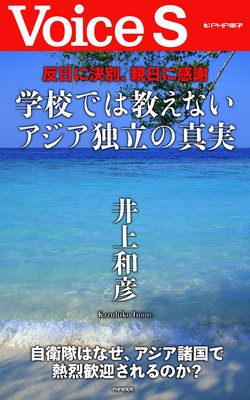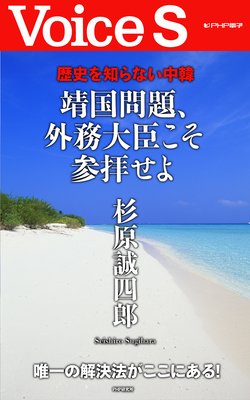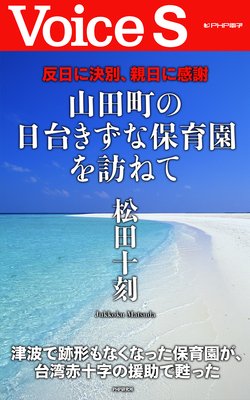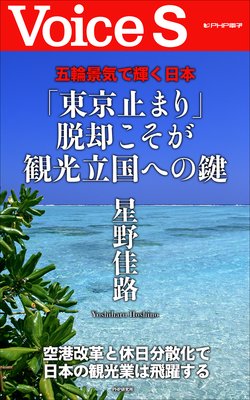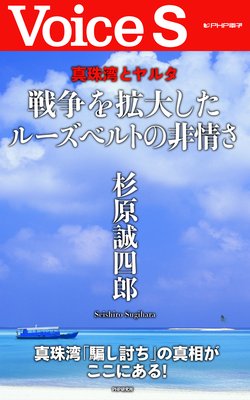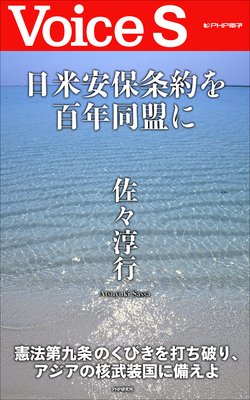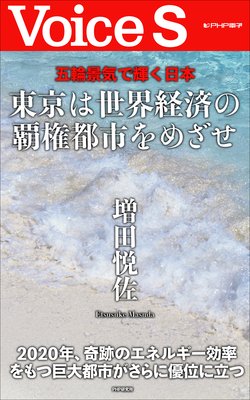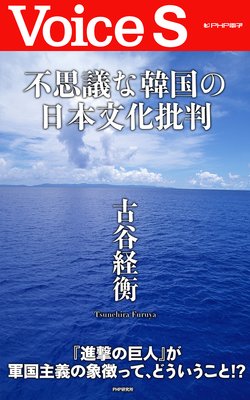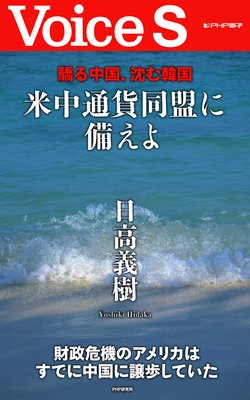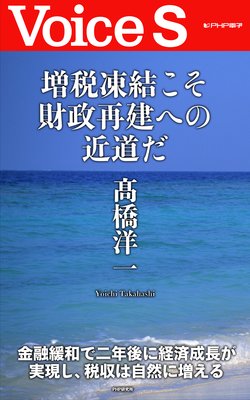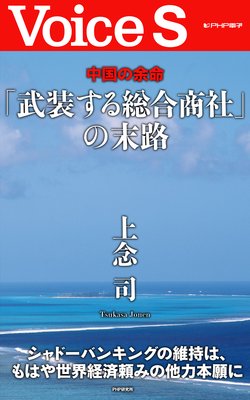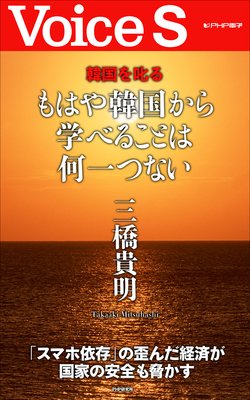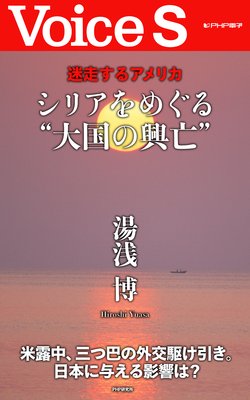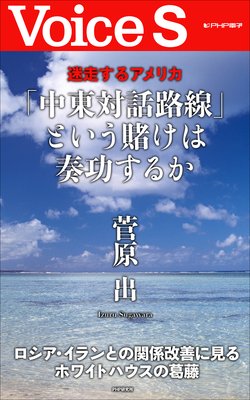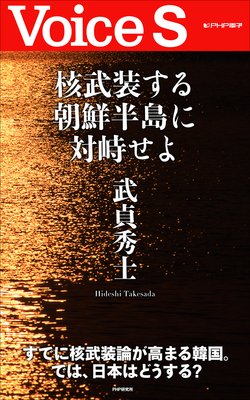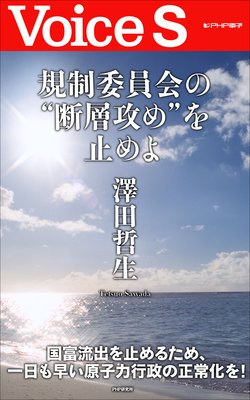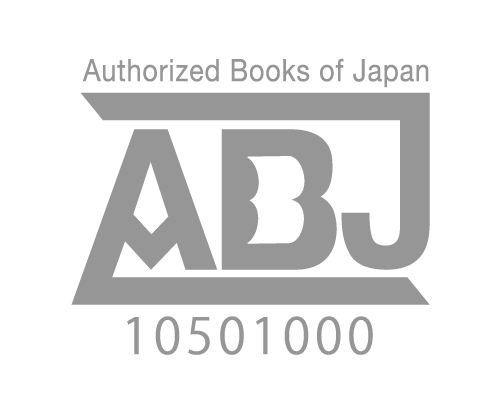検索結果
-
 実用書今、「戦後」が歴史になりつつある。戦後が対象化され、反省の材料となり、「あの時代がなんだったのか」が問われている。では「新しい危機」や「文明の大転換」が始まるのか? 何か途方もない危機が、あるいは輝かしい未来が来るとでもいうのか? 気鋭の論客が日本の近代の「条件」、そして私たちが置かれたジレンマとは何かを考察。
実用書今、「戦後」が歴史になりつつある。戦後が対象化され、反省の材料となり、「あの時代がなんだったのか」が問われている。では「新しい危機」や「文明の大転換」が始まるのか? 何か途方もない危機が、あるいは輝かしい未来が来るとでもいうのか? 気鋭の論客が日本の近代の「条件」、そして私たちが置かれたジレンマとは何かを考察。
本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年10月号掲載記事を改題し、電子化したものです。 -
 実用書1937年12月13日、南京陥落にともなう「南京大虐殺」の虚構を国民に伝えた「GHQ洗脳メディア」の一つに、NHKラジオ番組『眞相箱』がある。この番組の台本の編集は連合国軍最高司令部民間情報教育局をはじめ『ニューズ・ウィーク』や『ニッポンタイムス』、そして『朝日新聞』の協力によるものだった。南京大虐殺の捏造報道をひと目で暴く一冊。
実用書1937年12月13日、南京陥落にともなう「南京大虐殺」の虚構を国民に伝えた「GHQ洗脳メディア」の一つに、NHKラジオ番組『眞相箱』がある。この番組の台本の編集は連合国軍最高司令部民間情報教育局をはじめ『ニューズ・ウィーク』や『ニッポンタイムス』、そして『朝日新聞』の協力によるものだった。南京大虐殺の捏造報道をひと目で暴く一冊。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年12月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書日本をはじめフィリピン、ベトナムなどアジア各国の領海を平然と侵し、領土拡大を狙う中国。その主張がいかに論理性を欠き、歴史を無視しているかは誰もが知るところだ。しかし従来の日本は、正面切って中国の「無法の証拠」を打ち出せずにいた。
実用書日本をはじめフィリピン、ベトナムなどアジア各国の領海を平然と侵し、領土拡大を狙う中国。その主張がいかに論理性を欠き、歴史を無視しているかは誰もが知るところだ。しかし従来の日本は、正面切って中国の「無法の証拠」を打ち出せずにいた。
著者は、アジア極東経済委員会(ECAFE)が尖閣沖に膨大な海底資源が埋蔵する可能性を指摘した1969年まで、中国が尖閣諸島を「日本領」と記していた地図を入手。69年を境に一転、中国が尖閣を自国領と主張しはじめた厚顔無恥さ、露骨なアリバイ工作を白日の下に晒す。一次史料で構成された本作は、国際社会に「日本の理」を訴える最良の道具となるだろう。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2015年2月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書腐敗した組織「中共」を廓清させるべく、、エリート軍人で構成される人民解放軍のスパイ機関・CGRUが動き出す。北朝鮮全土制圧から崩壊に至るシナリオとは、そして半島に残された邦人の運命は?
実用書腐敗した組織「中共」を廓清させるべく、、エリート軍人で構成される人民解放軍のスパイ機関・CGRUが動き出す。北朝鮮全土制圧から崩壊に至るシナリオとは、そして半島に残された邦人の運命は?
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年9月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書『朝日新聞』の検証記事(2014年8月5日および6日付「慰安婦問題を考える」)は20年間、慰安婦問題を焚き付けておきながら「弁明すれども謝罪せず」の内容に終始した。慰安婦を女子挺身隊と一緒くたにした理由については「当時は、慰安婦問題に関する研究が進んでおらず、誤用しました」。だが著者は、1940年〜45年の『朝日新聞 朝鮮版』や朝日新聞社発刊の書籍など「朝日自身」がとっくに慰安婦の実態を報じていた事実を暴き出す。一次史料で明らかになる現代史の大虚報。
実用書『朝日新聞』の検証記事(2014年8月5日および6日付「慰安婦問題を考える」)は20年間、慰安婦問題を焚き付けておきながら「弁明すれども謝罪せず」の内容に終始した。慰安婦を女子挺身隊と一緒くたにした理由については「当時は、慰安婦問題に関する研究が進んでおらず、誤用しました」。だが著者は、1940年〜45年の『朝日新聞 朝鮮版』や朝日新聞社発刊の書籍など「朝日自身」がとっくに慰安婦の実態を報じていた事実を暴き出す。一次史料で明らかになる現代史の大虚報。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年10月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書NHK連続テレビ小説「マッサン」の舞台にもなった余市蒸溜所。日本で初めて本格ウイスキー製造の地に余市を選んだ竹鶴政孝(マッサン)。その道程はけっして平坦ではなかった。マッサンとリタの生涯を振り返る過程で判明した故郷・スコットランドとの思わぬ共通点とは。
実用書NHK連続テレビ小説「マッサン」の舞台にもなった余市蒸溜所。日本で初めて本格ウイスキー製造の地に余市を選んだ竹鶴政孝(マッサン)。その道程はけっして平坦ではなかった。マッサンとリタの生涯を振り返る過程で判明した故郷・スコットランドとの思わぬ共通点とは。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年12月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書いまや中国からもアメリカからも見捨てられはじめ、徐々に世界から「置いてきぼりになる韓国」。景気を支えるはずのサムスン、現代自動車グループにも精細がない。一時期、「日本企業は韓国企業に学べ」と報道されていたのは、いったい何だったのか。稀代の韓国評論で知られる著者による最新「沈没」事情。
実用書いまや中国からもアメリカからも見捨てられはじめ、徐々に世界から「置いてきぼりになる韓国」。景気を支えるはずのサムスン、現代自動車グループにも精細がない。一時期、「日本企業は韓国企業に学べ」と報道されていたのは、いったい何だったのか。稀代の韓国評論で知られる著者による最新「沈没」事情。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年11月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書「ピケティ『21世紀の資本』はけっして難しい本ではない。分厚いだけだ」。700ページを超える大著を明解に翻訳し、大ベストセラーとして世に送り出した翻訳者が、本書の誤解されがちな点や本書に忠実な解釈、さらに日本経済と世界経済をめぐる「考えるヒント」を教えてくれる。
実用書「ピケティ『21世紀の資本』はけっして難しい本ではない。分厚いだけだ」。700ページを超える大著を明解に翻訳し、大ベストセラーとして世に送り出した翻訳者が、本書の誤解されがちな点や本書に忠実な解釈、さらに日本経済と世界経済をめぐる「考えるヒント」を教えてくれる。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2015年3月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書中国は本当に海洋覇権を握れるのか? 2014年9月の香港民主化デモは、図らずも1989年の天安門事件の悪夢と拙速な習近平外交の失敗を明らかにしてしまった。中国にはアジアの支配など無理だということが、日高氏の軍事および国際政治の分析によって明らかになる。
実用書中国は本当に海洋覇権を握れるのか? 2014年9月の香港民主化デモは、図らずも1989年の天安門事件の悪夢と拙速な習近平外交の失敗を明らかにしてしまった。中国にはアジアの支配など無理だということが、日高氏の軍事および国際政治の分析によって明らかになる。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年12月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書『朝日新聞』の問題は慰安婦だけではない。日中国交正常化(1972年)の前、70年の国交回復交渉の時期において、ひたすら中国におもねった『朝日新聞』の報道姿勢こそ「侮日」と「反日」を生んだ原点である。以後、中国共産党に「強硬に出れば日本はいくらでも譲歩する」と思わせ、わが国に重大な禍根を残すことになる。その最たるものが戦時徴用訴訟をはじめ、日本企業に対して法外な金額を求める中国の賠償請求問題である。現代とまったく変わらない、1930年前後の「タカリの構造」が明かされる。
実用書『朝日新聞』の問題は慰安婦だけではない。日中国交正常化(1972年)の前、70年の国交回復交渉の時期において、ひたすら中国におもねった『朝日新聞』の報道姿勢こそ「侮日」と「反日」を生んだ原点である。以後、中国共産党に「強硬に出れば日本はいくらでも譲歩する」と思わせ、わが国に重大な禍根を残すことになる。その最たるものが戦時徴用訴訟をはじめ、日本企業に対して法外な金額を求める中国の賠償請求問題である。現代とまったく変わらない、1930年前後の「タカリの構造」が明かされる。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年11月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書存在を忘れ去られた幻の新聞「すがも新聞」。そこには、巣鴨プリズンの収容者たちが残した、貴重な肉声が記録されていた。
実用書存在を忘れ去られた幻の新聞「すがも新聞」。そこには、巣鴨プリズンの収容者たちが残した、貴重な肉声が記録されていた。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年1月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書アメリカの歴史を書き換えたシリア攻撃の中止、政治史上最悪ともいえる議会との関係――オバマ大統領の舵取りが世界を混乱に陥れるなか、わが国はいかにしてアメリカに対峙すべきなのか。辛口ジャーナリストが「迷走する超大国」を一刀両断する。
実用書アメリカの歴史を書き換えたシリア攻撃の中止、政治史上最悪ともいえる議会との関係――オバマ大統領の舵取りが世界を混乱に陥れるなか、わが国はいかにしてアメリカに対峙すべきなのか。辛口ジャーナリストが「迷走する超大国」を一刀両断する。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2013年11月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書2013年2月に刊行した『黙視』で農業と食の問題に真っ向から切り込んだ社会派作家が語る、TPP問題、農協改革のほんとうの論点。
実用書2013年2月に刊行した『黙視』で農業と食の問題に真っ向から切り込んだ社会派作家が語る、TPP問題、農協改革のほんとうの論点。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2013年8月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書「原発から出る核のゴミを棄てる場所(最終処分場)がないのだから、いますぐすべての原発を廃止すべきだ――」。こうした「脱原発派」の論調にエネルギー政策の専門家が徹底反論!
実用書「原発から出る核のゴミを棄てる場所(最終処分場)がないのだから、いますぐすべての原発を廃止すべきだ――」。こうした「脱原発派」の論調にエネルギー政策の専門家が徹底反論!
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年3月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書台湾、インド、フィリピン、インドネシア……宗主国の支配からアジア諸国を解放した日本軍。その偉業はいまでも讃えられ、日本そして日本人への感謝の声はいまも色あせることはない。
実用書台湾、インド、フィリピン、インドネシア……宗主国の支配からアジア諸国を解放した日本軍。その偉業はいまでも讃えられ、日本そして日本人への感謝の声はいまも色あせることはない。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年4月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書2013年12月、安倍首相は靖国神社参拝に踏み切った。著者が「快挙」と語るこの行動は、一方で中韓の反発やアメリカの失望を招いた。果たして日本は靖国問題にどう向き合っていくべきなのか。歴史教育の観点から「唯一の」解決法を提示する。
実用書2013年12月、安倍首相は靖国神社参拝に踏み切った。著者が「快挙」と語るこの行動は、一方で中韓の反発やアメリカの失望を招いた。果たして日本は靖国問題にどう向き合っていくべきなのか。歴史教育の観点から「唯一の」解決法を提示する。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年3月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書岩手県下閉伊郡山田町にある「日台きずな保育園」。もともと別の名前だった同園が、津波によって壊滅し、台湾の赤十字組織の支援によって再建を果たすまでを描いた日台友情の物語。
実用書岩手県下閉伊郡山田町にある「日台きずな保育園」。もともと別の名前だった同園が、津波によって壊滅し、台湾の赤十字組織の支援によって再建を果たすまでを描いた日台友情の物語。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年4月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書外国人観光客数が急増するなど、「追い風」が吹く日本の観光業。しかし、ほとんどの外国人が「東京止まり」になっているという課題を克服しなければ、観光業を真の「国際的な成長産業」にすることはできない。現状を突破する秘策を、ホテル経営の革命児が語った。
実用書外国人観光客数が急増するなど、「追い風」が吹く日本の観光業。しかし、ほとんどの外国人が「東京止まり」になっているという課題を克服しなければ、観光業を真の「国際的な成長産業」にすることはできない。現状を突破する秘策を、ホテル経営の革命児が語った。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2013年11月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書1941年12月8日、日本軍の真珠湾攻撃から始まった太平洋戦争。長い間、日本の「騙し討ち」とされていたが、その裏にはルーズベルト米大統領の驚くべき陰謀が潜んでいた。歴史教育の専門家が、いま日本人が知っておくべき歴史的事実を白日の下に晒す。
実用書1941年12月8日、日本軍の真珠湾攻撃から始まった太平洋戦争。長い間、日本の「騙し討ち」とされていたが、その裏にはルーズベルト米大統領の驚くべき陰謀が潜んでいた。歴史教育の専門家が、いま日本人が知っておくべき歴史的事実を白日の下に晒す。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年1月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書イスラム圏のテロ、北朝鮮のミサイル、中国との領土問題――脅威にさらされる日本がいまこそ考えるべき「危機管理」とは。国家安全保障の中核を担ってきた重鎮が、安倍政権に送る渾身のエール。
実用書イスラム圏のテロ、北朝鮮のミサイル、中国との領土問題――脅威にさらされる日本がいまこそ考えるべき「危機管理」とは。国家安全保障の中核を担ってきた重鎮が、安倍政権に送る渾身のエール。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2013年4月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書「巨大都市における平和で安全で快適な日常」という奇跡を体現する都市・東京。2020年の東京オリンピックは、日本文明の素晴らしさを世界にショーアップする絶好の機会だ――。舌鋒鋭い一流アナリストが提示する、まったく新しい都市経済論。
実用書「巨大都市における平和で安全で快適な日常」という奇跡を体現する都市・東京。2020年の東京オリンピックは、日本文明の素晴らしさを世界にショーアップする絶好の機会だ――。舌鋒鋭い一流アナリストが提示する、まったく新しい都市経済論。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2013年11月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書近年、韓国のネチズン(ネットユーザー)が、日本のアニメや映画、漫画に難癖をつけている。日本人から見たら「曲解」としか思えない韓国ネチズンの論理を見れば、日本政府の「クールジャパン」推進政策が破綻していることは火を見るより明らかだ。
実用書近年、韓国のネチズン(ネットユーザー)が、日本のアニメや映画、漫画に難癖をつけている。日本人から見たら「曲解」としか思えない韓国ネチズンの論理を見れば、日本政府の「クールジャパン」推進政策が破綻していることは火を見るより明らかだ。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年4月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書アメリカ高官二人による、北京への極秘訪問。ドルと人民元の共存体制を協議するためにセッティングされたこの会談は、今後の国際情勢にどのような影響を与えるのか。当代髄一のアメリカウォッチャーが日米中三カ国の行く末を占う。
実用書アメリカ高官二人による、北京への極秘訪問。ドルと人民元の共存体制を協議するためにセッティングされたこの会談は、今後の国際情勢にどのような影響を与えるのか。当代髄一のアメリカウォッチャーが日米中三カ国の行く末を占う。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年2月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書消費増税の効果は経済学的に認められず、むしろ景気を悪化させる――リフレ派の泰斗が語る、アベノミクスが打つべき「次の一手」とは。
実用書消費増税の効果は経済学的に認められず、むしろ景気を悪化させる――リフレ派の泰斗が語る、アベノミクスが打つべき「次の一手」とは。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2013年8月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書経済政策ですら権力闘争の道具にしてしまう、支那共産党内部の仁義なき戦いを見よ。
実用書経済政策ですら権力闘争の道具にしてしまう、支那共産党内部の仁義なき戦いを見よ。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2014年1月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書「スマートフォン依存」経済の歪みが、崩壊しつつある証左が見えた。もはや、韓国経済やサムスンに日本が学べることは何一つない。
実用書「スマートフォン依存」経済の歪みが、崩壊しつつある証左が見えた。もはや、韓国経済やサムスンに日本が学べることは何一つない。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2013年10月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書シリアをめぐる大国間の駆け引き。末に待つのは「超大国・アメリカの終焉」か? 産経新聞のベテラン記者がいまの国際情勢を読み解く。
実用書シリアをめぐる大国間の駆け引き。末に待つのは「超大国・アメリカの終焉」か? 産経新聞のベテラン記者がいまの国際情勢を読み解く。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2013年11月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書「従来の中東政策におけるパートナーであるイスラエル・サウジアラビア」と「化学兵器問題を外交的な手法で解決しようとするロシア・イラン・シリア」のあいだで股裂き状態になっているアメリカ。待つのは新しい中東秩序か、さらなる混乱か――。
実用書「従来の中東政策におけるパートナーであるイスラエル・サウジアラビア」と「化学兵器問題を外交的な手法で解決しようとするロシア・イラン・シリア」のあいだで股裂き状態になっているアメリカ。待つのは新しい中東秩序か、さらなる混乱か――。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2013年11月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書核実験やミサイル発射など、留まるところを知らない北朝鮮の暴走。その動きに対抗すべく、韓国ではすでに核武装を求める声が強まっている。中国、アメリカなどの思惑も錯綜するなか、日本の取るべき道は――。
実用書核実験やミサイル発射など、留まるところを知らない北朝鮮の暴走。その動きに対抗すべく、韓国ではすでに核武装を求める声が強まっている。中国、アメリカなどの思惑も錯綜するなか、日本の取るべき道は――。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2013年4月号掲載記事を電子化したものです。 -
 実用書原子力規制委員会は、これほどまでに歪みと矛盾に満ちている――「日本はいつから無法国家に成り下がってしまったのか」と憤る気鋭の研究者は、原子力行政の暗部をどう暴くのか。
実用書原子力規制委員会は、これほどまでに歪みと矛盾に満ちている――「日本はいつから無法国家に成り下がってしまったのか」と憤る気鋭の研究者は、原子力行政の暗部をどう暴くのか。
※本コンテンツは月刊誌『Voice』2013年8月号掲載記事を電子化したものです。